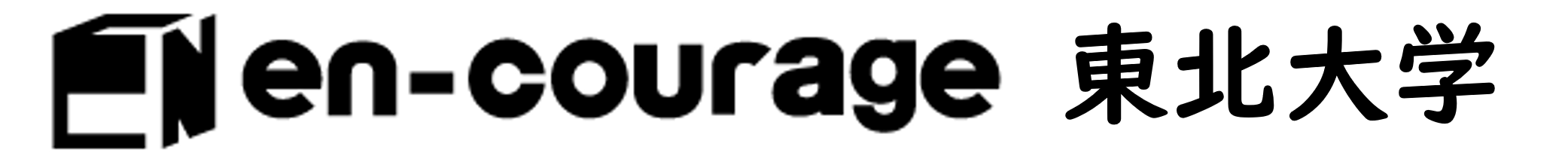公務員試験対策を順調に進めていても、突然始まる面接対策で「自分らしさ」を見失う受験生は少なくありません。
本記事では、国家一般レベルの勉強からスタートし、徹底的な「自己分析」を通じて公務員志望から大学院進学へと進路変更した一人の学生の経験を基に、公務員就活と自己分析について紹介します!
- 公務員就活の準備はいつから何をすべき?
- 生協の対策講座だけで十分?
- なぜ公務員就活こそ自己分析が重要なのか?
話を聞いた人:学部四年 公務員就活 大学院院進
① 夏までは何してた?
公務員試験の対策は、早い人で大学2年生の2月・3月頃から、遅くともゴールデンウィーク頃から始める人が多い印象です。私自身は、国家一般水準の勉強を中心に行っていましたが、実際に受験を考えていたのは地方公務員でした。
主な勉強方法は、生協が提供する対策講座を利用しました。具体的には、講義の動画を視聴し、その後、問題集を解いて復習するというサイクルです。夏頃までは、試験範囲の広い教養科目を重点的に進めていました。
② 秋からの動き方
夏を終え、秋からは専門科目の勉強に軸足を移しました。また、この時期から本格的に面接対策も開始します。
面接練習についても、生協の対策講座を中心に利用していました。周囲に公務員就活をしている友人が少ない環境だったため、エンカレでは公務員の先輩方と話す機会を作ったり、自分の現状を周りの就活生と比較したりして、モチベーション維持や情報収集に役立てていました。
③ 公務員就活で自己分析って大事?
今振り返って一番後悔しているのは、「もっと早く自己分析を徹底的にやればよかった」ということです。
公務員試験対策では、秋頃になると突然面接対策が始まりますが、その時になって初めて「自分はどのような人間で、なぜ公務員になりたいのか」を具体的にどう表現すれば良いか分からず戸惑いました。それまでの自己分析で行っていたものは心理テストのようなものが主で、表面的な理解に留まりがちでした。
私が最も重要だと感じたのは、モチベーショングラフです。自分の人生を1歳から現在まで細かく振り返り、「どの時期に楽しみややりがいを感じたか」を視覚化することで、自分がどういう人間で、何にモチベーションを感じるのかの源泉を知ることができました。
その結果、大学3年生の2月になって自己分析を徹底的に行ったとき、「自分が本当に楽しいと感じること、将来的に追い求めたいことは公務員の仕事ではない」と気付き、最終的に大学院進学という進路を決めました。それまでは、公務員試験は突飛な内容のESより平均点以上が取れる書き方で合格できると考えていたため、型通りの面接内容で進めていました。
④ 自己分析はどうやった?
本格的な自己分析は、公務員就活から大学院進学への切り替えを検討し始めた3年生の2月から開始しました。
モチベーショングラフの作成と壁打ち
心理テストのような形式はほとんど行わず、時間をかけたのはモチベーショングラフの作成と「壁打ち」です。
モチベーショングラフは、自分で人生の楽しかったことや頑張ったことを思い出しながら作成した後、民間就活の支援者(団体代表者)などプロの視点を持つ人にそれを見せ、1歳から21歳までの出来事について「それはこういうことだったの?」と細かく言語化してもらう作業を行いました。この対話を通じて、自分のモチベーションの源泉が明確になり、「本当にやりたいこと」まで落とし込むことができました。
他者との対話で深める
自己分析には約1ヶ月を費やし、グラフ作成だけでなく、自分自身との対話、そして何よりも他人との対話に最低でも10時間以上を費やしました。
やりたいことを10個ほど洗い出した後、その中でも特に自分の心が震えること、将来もずっと継続したいことを見極めていきました。その結果、フリースクールの運営などの実践を通じて関わってきた「NPOの研究」を続けることが、最もモチベーションが上がるという結論に至りました。
壁打ち相手は、学生同士だけでなく、社会に出ていないと得られない意見を求めて企業の人事(顧問や社長)やゼミの教授など、最低でも5人の大人と話しました。彼らは必ずしも自分の意見を肯定するのではなく、「でも社会はこうだよね」「それをもっと具体的に言うと?」と議論を重ねてくれました。そのおかげで、自分の考えがまとまり、より具体的になったと感じています。
こうした自己分析と他者との対話を通して、「社会に出る前に大学院で実践を積み、専門性を身につけてから社会に出たい」という確固たる目標が見つかり、3年生の2月から3月にかけて大学院進学を決意しました。